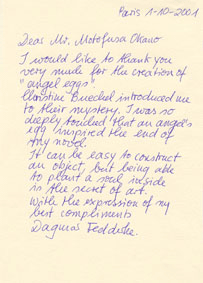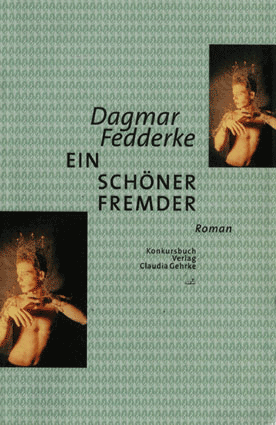<美男子の異邦人> ムスタファは不法に入国し、この町にやって来た。うまくいった。大金を、親戚と友だちのあり金をすべて使い果たした。たくさんの別れの痛み。金のほかに、希望も与えてくれた。旅立たせてくれた。そして、遠い異国から、金と富とを家に送るように彼に託した。なのに、旅の途中で彼は災難に遭った。彼の友だちの悪い仲間が彼の持ち物を全部奪い取ったのだ。まるで深い沼地に一歩一歩はまっていくようだった。そこから出るために彼は一歩ずつ足を引き上げなければならなかったが、そうすることによってさらに深くはまり込んでいくのだった。もし、十分な筋力がなかったら、この異国とこの町にたどり着く前に
死んでいただろう。彼にとってこの新天地は、いつもこの町と、一枚の紙切れに書かれたある住所からなりたっていた。彼の心臓や目玉がそうであるように、そ
の紙切れは、すべての脅威に際しても彼のそばにとどまっていた。けがをした動物のように、彼はようやくその家に這い込んだ。けれどもその住所は留守だっ
た。ドアには鍵がかかっていた。彼は漂着した人間のように階段の上で眠った。黒人の女が彼の前に現れた。彼はその女のついていった。まるで、自分の星を去る者のように。でも、信頼の気持ちからではなく、そこしか行くところがなかったからだった。彼女は彼をあるアパートの一室に連れていった。彼に温かいスープを
飲ませた。彼に毛布を掛けた。そして、彼を乱暴に起こした。「出ていけ。すぐ出ていけ。」彼には彼女の言葉は理解できなかったが、彼女の意味するところははっきりわかった。彼は例の紙切れを見せた。彼女は首を振り、肩をすくめた。そして戸口に彼を押しやった。外へ。一歩一歩、沼地に入っていく。どうして彼はこれに慣れることができないんだろう。どうして、彼の魂は体より痛むんだ。スープを飲ませてもらったから? よろけながら通りに出た。 彼は目的地に着いた。
でも、その目的地は目的地ではなかった。彼は自分がどこにいるのか知らない。この世界は人間でいっぱいだ。みんなどこかへ行く。一日に百回も出かけて、一日に百回も行きたい場所にちゃんと着く。おれは一回だけたどり着いたのに、おれの行きたかった場所は存在しなかった。つまり、おれはどこにもたどり着かなかったんだ。ああ、どこでもないところからどこかへ行くのは、なんて大変なんだ。
p6.l3-p7.l5
ムスタファのひげは伸び放題になっていた。一時しのぎに町の共同水場で顔を洗った。腹を空かして近くの公園にたどり着いた。ベンチの上で疲れ切った体を休
めた。何をしたいかを知っていて幸せそうに見える、彼の周りの人々の満たされた生活以外は、彼には何も見えず、何も聞こえなかった。 木陰のベンチの上で眠りたかったが、一人の老婆がそこに腰掛けてきて、彼が脚を伸ばすのを邪魔した。彼女は続けざまに話しかけた。彼女は、彼が子供、孫、離婚、施設、痛み、薬といった言葉以外は全く理解していないことを無視した。静かにしてくれ。彼は思った。黙れ、どっか行け、婆さんが行かないんなら暴力を加えてやる。しかし老婆は落ち着きはらってカバンから編み物を取り出した。毛糸玉と一緒に財布が滑り落ちた。毛糸玉は砂の上に落ちた。彼女は難儀そうに静脈瘤のある足の上に身をかがめた。財布はムスタファの脇にある。財布はそこにあるんだ。老婆が編み物を続けるすきに、彼は慎重に財布を拾い上げた。老婆は気づいていない。気づいていたら殺さなくてはならなかったろう。財布には何か食べるのに十分な金が入っていた。彼はあまり遠くまで行かないところで、ステーキを注文した。温かい肉。彼はそれをガツガツ食べた。そのとき、ムスタファが血の滴るステーキを貪欲に食べているのを見ていた男が声をかけてきた。「写真を撮ってもいいですか。いい歯をしてらっしゃるので。」ムスタファにはこの褒め言葉がわからなかった。心理学的な訓練を受けていないので、彼は分析も解釈もできず、ただ、感じるだけだった。一瞬にして二つの衝撃が走った。血が筋肉に新しい力を運んだ。つま先から眉毛まで震えた。脳に光がちかちか差して、突然の電流が、世界の目に見える部分に対する彼のまなざしを切り刻んだ。おれから何を欲しいんだ。こいつが欲しがるなんてばかげてる。また新しい沼だ。おれの歯。おれはもう歯ほどの価値もないのか。食ったら思い出したぞ、おれは大きくって、美しいんだ。おれは耐え抜いたんだから、誰もおれを笑いものにはできないんだ。
p7.l6-p8.l7
彼は立ち上がり、殴る構えをした。この男を殺したかった。嘲笑から身を守るために・・・。このとても我慢のならない男と、レストランで彼の周りに座っている、仕事を見つけるのに何の心配もないすべての人間に、彼が歯以上のものであることを見せたかった。しかし、その男はうまくよけた。ムスタファの拳は宙に舞った。「どうか」一瞬の驚愕の後、この男は言った。そして、ムスタファの目をじっと見つめた。「どうか、自己紹介させてください。私はルッツと申しまして歯医者をしています。私は素晴らしい歯につい魅せられてしまいまして。あなたの歯があんまり素晴らしいので。」 ムスタファは口を開けた。血の滴るステーキのカスがまだ歯にはさまっていた。のどに言葉が引っかかって出てこない。彼の瞳孔は信頼すべき定点を探してめまぐるしくくるくる動いた。しかし、そんな点は見つからない。彼は支えを失ってよろけた。どちらかというとがっしりした彼の体は、後ろ向きに大きな木製の椅子の上に倒れた。その椅子は彼の重みで壊れた。 歯医者は彼の上に屈み込んだ。職業からくる習慣で、彼は失神しているムスタファの唇の間に指を挟み込んだ。そして、左の瞼を押し上げた。 ウェイターが急いでやって来た。「何でもないんですよ。ただ失神しただけです。私は医者でして。すみませんがお勘定をお願いします。それからタクシーを呼んでください。」と、ドクタールッツはしっかりした調子で言った。ウェイターは静かに立ち去った。彼が勘定書を計算している間に、気絶していたムスタファは気がついた。しかし、頭は朦朧としている。助け起こされるままになり、前方を見つめ、誰かが彼のステーキ代を払い、タクシーに乗せたことにも気づかなかった。 ずいぶん後になって彼は意識を取り戻した。そこは奇妙な光景が広がっていた。彼は公園のベンチで寝ているのではなく、心地よい、肘掛けのついている椅子に寝ていた。その椅子には足台までついていた。彼の上に見知らぬ男の顔が現れた。その男は口を動かした。口が声を出した。その声はまるで小さな女の子たちがボールを追って校庭を駆け回るように、よく、お互いにあちらこちらへさまよった。みんなが一度そのボールにさわろう、蹴ろうとする。同時に、何も意味ないことは単純に愉快なので、大笑いする。
p8.l8-p9.l6 この大柄の、幾分まだ朦朧としていたがっしりした男は、これらの小さくて上品なボールけりが何を言っているのか、理解しようとした。難儀して耳を澄ませて、それらの声を言葉にまとめた。いくつかの言葉が文を構成している。でも意味を理解しないと完全な文の意味は分からない。意味は記憶から作られる。彼は何も思い出せない。どうやってここに来たのか、どこの部屋にいるのか。以前、ここに来たことがないことは確かだ。彼の手足、神経、そして筋肉だけがそれを知っている。彼の体の中にはステーキが血管に残した熱が巡っていた。もし、彼の具合がよくなったのなら、どこにいようがどうでもいいじゃないか。もしかしたら、おれは死んで、ここは天国なのかもしれない。 長い「あーあ」という声とともに、銀の前掛けの巻かれたのどから彼は固まりを吐
き出した。その前掛けは、ゴム手袋と布巾でもって、歯医者がまさにこのために、彼の顎の下に用意しておいたのだ。「これで楽になったでしょう。」歯医者はそう言って、まだ半分よく見えないムスタファの目に励ますようにほほえんだ。ムスタファは障害物を吐き出した。 わざと、ドクター・ルッツは彼に背を向け、ムスタファの前掛けを台の上に置いた。彼はわざとそうしたのだ。彼は、再び意識を取り戻したこのがっしりした男に襲いかかれる機会を与えたのだ。十秒待ったが、何の攻撃も感じないので、彼はこの男が天からの贈り物だと悟った。ムスタファの筋肉、口、歯は彼の役に立つだろう。褒美として、彼はこの奇跡のように発見された男に注射をした。 ・・ゆっくり休むといい。覚醒と昏睡の間でゆっくり休むんだ。ここにランプを置いておこう。君の瞼が閉じたら、私の大きな丸いライトを点けるよ。専門的に両脇から君の口を開いて器具で固定して、素晴らしい歯をできるだけ開くんだ。私のカメラが口の中から、様々な角度で撮影できるように。ああ、このときを生涯長く夢見てきたよ。夢が叶う! こんなことが実現するなんて! 私は世界で一番の幸せ者だ。
p9.l7-p10.l3
彼は写真を撮った。これらの写真は口腔内調査の医学史に受け入れられるだろう。それについて、彼は確信していた。歯根の組織は美しくそろっている、膿瘍もない、何のダメージもないこんな歯は、レントゲンなんかには撮らないぞ。全く健康な歯だ。暗い部屋で彼は喜びをほとんど押さえきれなかった。新しいフィルムはどこだ? もっと詳細を撮りたい。今、何時だ? 麻酔はあとどのくらい効いてるんだ? そうだ、もう一本麻酔を打とう。さあ、撮影だ。完璧な写真を撮らなくては。 長い夜が明け、夢中になっていたドクター・ルッツも朝日が差しているのに気づいた。彼は素晴らしい業績を上げた。すべてをやった。彼の素晴らしい歯の持ち主には、できるだけ早く目覚めてもらわないといけない。助手や患者が来る頃までには椅子に腰掛けさせなくてはならない。しかし、口を開けたままのこのがっしりした大柄の男は自力で起きあがれない。どこかに消えてくれればいいのに。 麻酔の量が多すぎたか。さて、どうしよう。 ドクター・ルッツはもう一度彼の状況を思い浮かべた。 助手のヘレン・クレマーはスタイルがいい。彼女の褐色の足は健康サンダルを履いていてもセクシーに見える。彼女の丸みを帯びた肘はなんとなく少女のようだ。ヘレンは二重代半ばだが、なんというか娘らしさがある。ドクター・ルッツは一人でほほえんだ。 彼女はいつも石膏をかき混ぜるとき、大量に作りすぎる。彼女には目測能力がない。しかし、親しみのある少し上を向いた鼻、陽気な目をしている。ドクターの鉄灰色のまなざしに比べたら、それは患者にいい印象を与える。中でも彼女の歯は宣伝効果抜群である。彼は彼女の歯を治したのだ。いや、まあ! まったく、直す必要があった。彼女の歯並びはメチャクチャだった。彼は輝かしい成果でもって、自分の技術を証明することができた。しかし、メチャクチャだったのは歯並びだけではないが・・・。
つづく
トップへ戻る↑